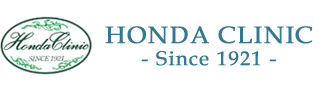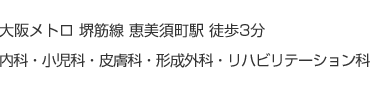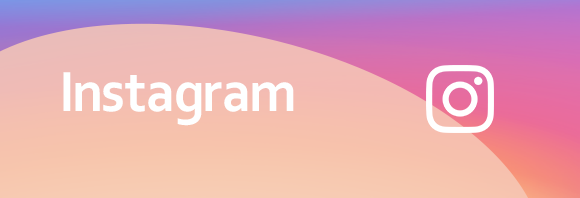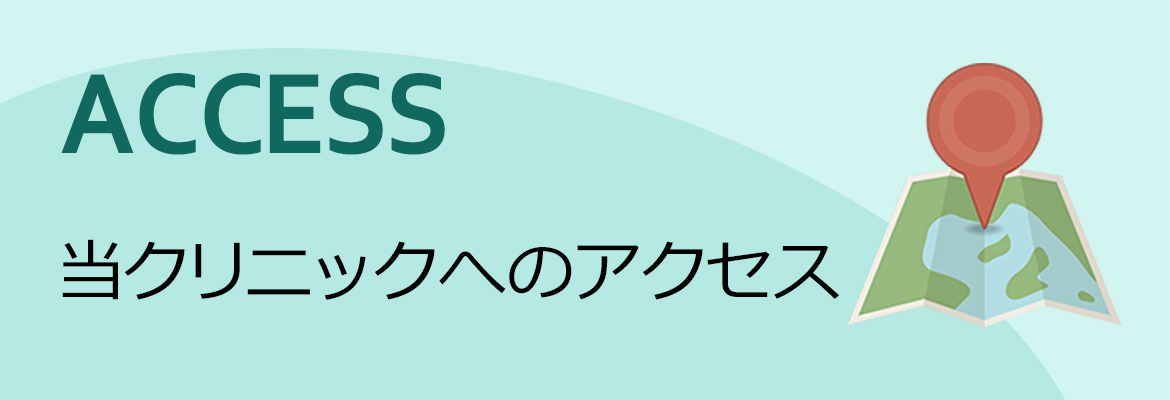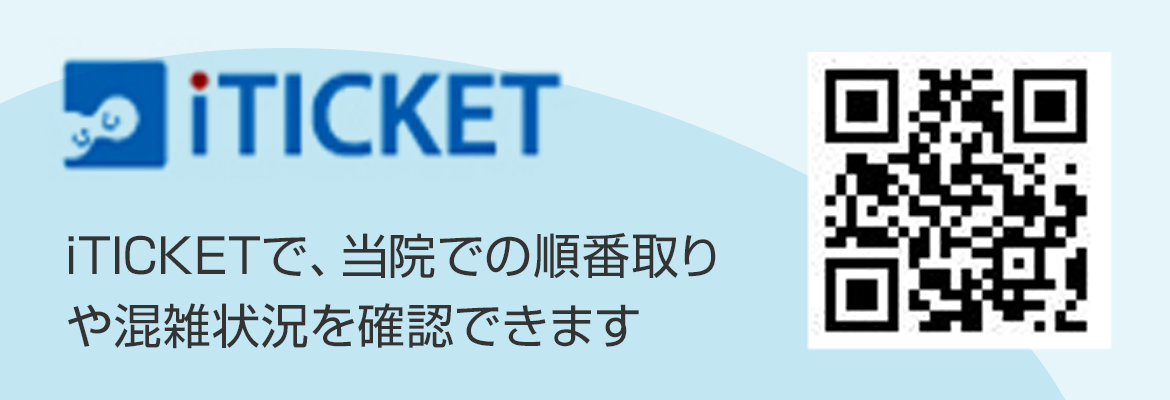お役立ちコラム 2025年8月
2025年 8月 4日 もう不安にならない!水難事故の原因と、今日からできる7つの対策

夏が近づき、水辺でのレジャーが楽しみな季節になりました。しかし、水難事故のニュースを目にするたびに、不安を感じる方もいるのではないでしょうか。この記事では、水難事故の原因を詳しく解説し、今日から実践できる具体的な対策を7つご紹介します。あなたと大切な人の命を守るために、水難事故のリスクを理解し、安全な水辺の楽しみ方を学びましょう。
水難事故の現状と課題
水難事故は、私たちの身近に潜む危険な問題です。水辺でのレジャーが増える夏場を中心に、毎年多くの命が失われています。このセクションでは、水難事故の現状と課題を把握し、私たちが直面している問題について理解を深めていきます。
水難事故の発生件数と傾向
水難事故は、年間を通して発生していますが、特に夏場に集中する傾向があります。レジャー目的での水辺の利用が増えることが主な原因です。過去のデータからは、事故発生場所として、海、川、湖沼、プールなど、さまざまな場所が挙げられています。また、年齢層別に見ると、子どもから高齢者まで、幅広い年齢層で発生しており、誰にとっても他人事ではないことが分かります。事故の発生件数は、年によって変動がありますが、依然として高い水準で推移しており、対策の強化が急務です。
水難事故の原因トップ3
水難事故の原因は多岐にわたりますが、主なものとして以下の3つが挙げられます。それぞれの原因と注意点を見ていきましょう。
原因
- 遊泳中の事故:泳ぎの未熟さ、体力不足、水温の低さ、波や流れの影響などにより、溺れてしまうケースです。特に、子どもの場合は、水深の見誤りや、急な深みに足を取られることなど、注意が必要です。
- 転落:堤防や岸壁からの転落、ボートからの転落など、不注意やバランスを崩すことによって発生します。飲酒後の行動や、足場の悪い場所での移動も危険性を高めます。
- 自然現象:離岸流や急な増水、雷など、自然現象による事故も少なくありません。特に、海や川では、天候が急変することがあり、注意が必要です。
これらの原因を理解し、それぞれの状況に応じた対策を講じることが重要です。
水難事故を防ぐための7つの対策
水難事故から身を守るためには、具体的な対策を知り、実践することが重要です。ここでは、水難事故を未然に防ぐための7つの対策をご紹介します。これらの対策を参考に、安全に水辺でのレジャーを楽しみましょう。
- ライフジャケットを着用する
水辺での活動においては、必ずライフジャケットを着用しましょう。特に、泳ぎに自信がない人や子どもは必須です。ライフジャケットは、万が一の事故の際に、浮力を確保し、溺れるリスクを軽減します。適切なサイズのライフジャケットを選び、正しく着用することが大切です。着用する際は、バックルやベルトがしっかりと締まっているか確認しましょう。 - 監視員のいる場所で遊ぶ
海やプールなど、監視員がいる場所で遊ぶようにしましょう。監視員は、水難事故の発生を未然に防ぐための注意喚起や、万が一の事故の際に迅速な対応をしてくれます。監視員の指示に従い、安全に水遊びを楽しみましょう。 - 子どもから目を離さない
子どもは、大人の目が届かないところで、思わぬ事故に遭うことがあります。水辺で子どもを遊ばせる際は、絶対に目を離さないようにしましょう。特に、小さな子どもは、水深が浅い場所でも溺れる危険性があります。子どもの行動範囲を把握し、常に注意を払い、危険を回避できるようにしましょう。 - 天候や水温に注意する
天候や水温は、水難事故のリスクに大きく影響します。雨天時や強風時には、水辺での活動を控えましょう。また、水温が低い場合は、体温が奪われやすく、低体温症になる危険性があります。体調に合わせて、無理のない範囲で水遊びを楽しみましょう。天気予報を確認し、安全な状況で活動することが重要です。 - 飲酒後の遊泳はしない
飲酒後の遊泳は、判断力や運動能力が低下し、事故のリスクを高めます。飲酒した場合は、絶対に泳がないようにしましょう。また、水辺でのレジャーを楽しむ際は、飲酒量を控え、節度ある行動を心がけましょう。 - 単独行動を避ける
単独での水辺での活動は、万が一の事故の際に、誰にも気づかれず、救助が遅れる可能性があります。できる限り、複数人で行動し、互いに注意を払い、安全を確保しましょう。単独行動をする場合は、家族や友人に、どこで何をするのかを伝えておくようにしましょう。 - 応急処置を学ぶ
万が一、水難事故が発生した場合に備えて、応急処置の方法を学んでおきましょう。心肺蘇生法や、人工呼吸の方法を習得しておくことで、救命できる可能性が高まります。地域の講習会などに参加し、知識と技術を身につけましょう。
場所別の安全対策
水難事故は、場所によって注意すべき点が異なります。海、川、プール、それぞれの場所での安全対策を知り、水難事故のリスクを最小限に抑えましょう。
海での注意点
海は、水深が深く、波や潮流があるため、特に注意が必要です。まず、遊泳禁止区域や、危険な場所には近づかないようにしましょう。離岸流が発生しやすい場所や、急に深くなっている場所など、危険な場所は事前に確認しておくことが大切です。また、波が高い日や、風が強い日は、遊泳を控えましょう。体調が悪いときも、無理に海に入ることは避けましょう。海では、ライフジャケットの着用が非常に重要です。泳ぎに自信がある人も、必ず着用するようにしましょう。海での遊泳に慣れていない場合は、監視員のいる場所を選び、指示に従って安全に楽しみましょう。熱中症対策として、こまめな水分補給も忘れずに行いましょう。
川での注意点
川は、流れが速く、水深も場所によって異なるため、注意が必要です。川で遊ぶ際は、増水に注意し、大雨が降った後や、雨が降りそうなときは、川に入るのを控えましょう。川底は、石や岩で滑りやすくなっているため、注意して歩きましょう。深い場所に足を踏み入れたり、急な流れに巻き込まれたりしないように、注意が必要です。川での遊泳に慣れていない場合は、浅瀬で遊ぶようにしましょう。川には、急に深くなっている場所や、底が見えない場所もあります。ライフジャケットを着用し、安全に配慮して遊びましょう。川は、自然の中で遊べる貴重な場所ですが、危険も潜んでいます。川の特性を理解し、安全に配慮して楽しみましょう。
プールでの注意点
プールは、比較的安全な場所ですが、それでも注意すべき点があります。プールの水深は、場所によって異なります。子どもの身長に合わせた水深のプールを選び、必ず大人が付き添いましょう。プールの底が見えない場合は、無理に泳がないようにしましょう。プールの周りは、滑りやすくなっています。走ったり、ふざけたりしないようにしましょう。プールの利用規約を守り、監視員の指示に従いましょう。熱中症対策として、こまめな水分補給と休憩を心がけましょう。プールは、楽しい場所ですが、安全に注意して、水難事故を防ぎましょう。
水難事故発生時の応急処置
水難事故は、いつどこで発生するかわかりません。万が一の事態に備えて、適切な応急処置の方法を理解しておくことは、命を守るために非常に重要です。このセクションでは、水難事故が発生した場合の救助方法、心肺蘇生法、そして救急車を呼ぶ際の注意点について解説します。
1.救助方法
水難事故に遭遇した人を見かけたら、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。安全を確保できる場合は、直ちに救助に向かいましょう。救助の際には、以下の点に注意してください。
- 大声で応援を呼ぶ: 周囲の人々に助けを求め、協力を得ましょう。救助者が複数いる場合は、役割分担をして効率的に救助を行いましょう。
- 浮力のあるものを利用する: 浮き輪、ペットボトル、クーラーボックスなど、浮力のあるものを投げて、溺れている人に掴ませましょう。直接水に入る場合は、必ずライフジャケットを着用しましょう。
- 安全な方法で救助する: 岸からロープを投げたり、棒を差し出したりするなど、安全な場所から救助を試みましょう。泳いで救助する場合は、溺れている人に近づきすぎないように注意し、背後から近づき、顎を上げて呼吸を確保するようにしましょう。救助者の安全も確保しながら、落ち着いて救助を行いましょう。
2.心肺蘇生法
溺れている人を救助したら、直ちに心肺蘇生法(CPR)を開始しましょう。心肺蘇生法は、心臓と呼吸が停止した人に対して、血液循環と呼吸を補助するための応急処置です。心肺蘇生法の手順は以下の通りです。
- 意識の確認: 意識がない場合は、大声で呼びかけたり、肩を叩いたりして、反応があるか確認します。反応がない場合は、心肺蘇生を開始します。
- 呼吸の確認: 呼吸をしていない、または普段通りの呼吸をしていない場合は、胸骨圧迫と人工呼吸を行います。呼吸がある場合は、回復体位にして呼吸の状態を観察します。
- 胸骨圧迫: 胸の真ん中に両手を重ね、体重をかけて1分間に100~120回の速さで圧迫します。胸が約5cm沈むように圧迫しましょう。
- 人工呼吸: 胸骨圧迫を30回行ったら、人工呼吸を2回行います。人工呼吸は、気道を確保し、口から息を吹き込みます。人工呼吸が難しい場合は、胸骨圧迫のみを継続します。
- AEDの使用: AED(自動体外式除細動器)が利用できる場合は、AEDの指示に従い、電気ショックを行います。AEDは、心臓の動きを正常に戻すための装置です。
- 継続的な処置: 救急隊が到着するまで、心肺蘇生法とAEDの使用を継続します。心肺蘇生法は、一刻を争う処置です。迷わずに、迅速に行いましょう。
3.救急車を呼ぶ
水難事故が発生し、心肺蘇生法が必要な場合は、直ちに救急車を呼びましょう。救急車を呼ぶ際には、以下の点に注意してください。
- 119番通報: 119番に電話し、救急車を要請します。住所、事故の状況、負傷者の状態を正確に伝えましょう。
- 場所の特定: 事故発生場所を正確に伝えられるように、住所や目標物を事前に確認しておきましょう。海や川の場合は、地名や目標物、目印となるものを伝えると、救急隊が到着しやすくなります。
- 電話を切らない: 救急隊からの指示があるまで、電話を切らないようにしましょう。救急隊の指示に従い、必要な情報を伝え、応急処置を行いましょう。
- 救急隊の到着を待つ: 救急隊が到着するまで、心肺蘇生法を継続し、救急隊に引き継ぎましょう。救急隊の到着を待ち、指示に従いましょう。
水難事故は、適切な応急処置を行うことで、救命できる可能性が高まります。心肺蘇生法や救急車の呼び方を理解し、万が一の事態に備えましょう。
まとめ:水難事故から身を守るために
この記事では、水難事故の原因と対策について解説しました。水難事故は、誰にでも起こりうる身近な危険です。しかし、適切な知識と対策を講じることで、そのリスクを大幅に減らすことができます。
ライフジャケットの着用、監視員のいる場所での遊泳、子どもの見守りなど、今日からできる対策はたくさんあります。また、海や川、プールなど、場所別の注意点も理解しておくことが大切です。万が一の事態に備えて、応急処置の方法を学ぶことも重要です。
水辺での安全対策を徹底し、あなたと大切な人の命を守りましょう。安全な水辺の楽しみ方を実践し、水難事故のない、楽しい思い出をたくさん作ってください。
2025年8月1日 監修者 本田 秀明

本田クリニック
〒556-0005
大阪府大阪市浪速区日本橋5-18-21
TEL 06-6641-2181